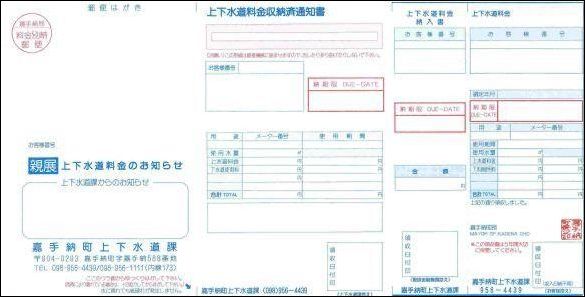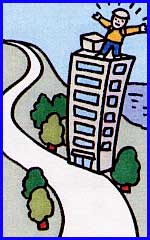【防災無線の聞き直しサービス(電話番号)】
○防災行政無線を放送24時間後まで電話で聞き直すことができます。
○防災無線を聞き逃した時など、内容を確認できますのでご利用ください。
電話番号 098-921-9136(嘉手納町防災行政無線聞き直しサービス)
※ おかけ間違いにご注意ください。
【WEB版 防災マップシステム 】
○スマートフォンやパソコンで嘉手納町防災マップシステムが利用できます。
○津波・高潮・土砂災害等 地図切り替えにより災害ハザード情報を確認できます。
○ご自身の位置情報が地図上に表示され、各種災害の危険想定区域内との照会ができます。
○避難所・避難場所・子供110番施設など確認できます。
⇩ 嘉手納町WEB防災マップはこちらから
https://map.town.kadena.okinawa.jp/
⇩ 携帯電話用 QRコード
![qr_out[1].png](/life/qr_out%5B1%5D.png)
【防災マップ(令和元年度 作成版)】
①嘉手納町防災マップ(冊子版 表紙・背表紙).pdf
②嘉手納町防災マップ(冊子版 町長挨拶・自由帳).pdf
③嘉手納町防災マップ(冊子版 目次).pdf
④嘉手納町防災マップ(冊子版 防災の知識).pdf
⑤嘉手納町防災マップ(冊子版 防災の知識 英訳).pdf
⑥嘉手納町防災マップ(冊子版 嘉手納町の見どころ).pdf
⑦嘉手納町防災マップ(冊子版 嘉手納町の見どころ 英訳).pdf
⑧嘉手納町防災マップ(冊子版 史跡てくてくマップ).pdf
⑨嘉手納町防災マップ(冊子版 牽引図・防災マップ).pdf
⑩嘉手納町防災マップ(冊子版 災害予測図).pdf
⑪嘉手納町防災マップ(冊子版 主要施設一覧・避難三原則).pdf
災害の心構え 1枚タイプ(ポケット版).pdf
防災マップ 1枚タイプ(ポケット版).pdf
【防災マップ(平成25年度 作成版)】
嘉手納防災マップ表紙.pdf地震災害・津波災害.pdf
竜巻災害・普段からの備え.pdf
台風・大雨・土砂災害.pdf
【嘉手納町地域防災計画】
表紙・目次.pdf
1編.基本編(総則、基本方針).pdf
2編.予防計画(地震・津波編).pdf
3編.予防計画(風水害等編).pdf
4編.応急対策計画.pdf
5編.復旧復興計画.pdf