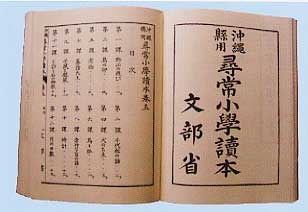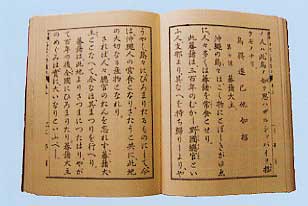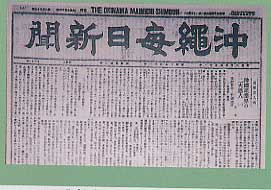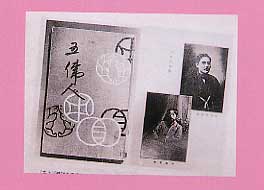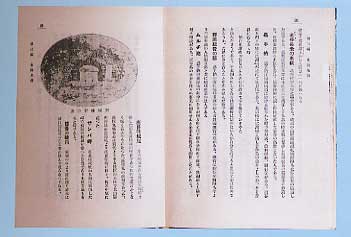| 2 1800 ~ 1900 年代の記録(近代) | ||||||||
| 教科書の中に見る野國總管 | ||||||||
| 歴史の本や家譜の中に野國總管の功績がたたえられて記されるようになり、記録として残されることになりますが、人びとが広く野國總管の名まえを知るようになるのは、明治時代になって学校の教科書に掲載されるようになってからです。 1879 年、琉球王国から沖縄県に変わってから、沖縄でもようやく学校に行く子どもたちがふえていきます。小学校でははじめ、全国と同じように『読書入門』(1886年)と『尋常小学校読本』(1887 年)という文部省でつくられた教科書が使われていました。しかし、日本本土と気候や風土、それに〝ことば〟の異ことなる沖縄県と北海道では同じ教科書を使うことは、都合が悪いということで、特別用教科書をつくることが認められます。沖縄県では、郷土の風物や代表的な人物を教材にした『沖縄県用尋常小学校読本』(1897 ~99 年)が発刊されることになります。 特別に編集された教科書は、1904 年に国の定めた教科書が採用されるまでの5年間使われることになりました。その中で、沖縄の偉人のひとりに野國總管が「蕃藷大主」として取りあげられたのです。教科書には、野國總管が中国から甘藷の苗を持ち帰って沖縄を救い、その後、甘藷が薩摩を経て全国に広まり、多くの国民に恵みをもたらしたと記述されています。 野國總管が持ち帰った甘藷の恩恵が、沖縄だけでなく全国を救ったという記述は、とても深い意味があるといえます。当時、沖縄が全国から異質な地域(本土とは違う特別なところ)と見られていた時代や沖縄県のおかれていた社会的背景を考えると、野國總管の功績をたたえて教科書にのせることで、沖縄の子ども達に日本国民の一員としての自信と誇りをもたせるねらいがあったのだと思います。 |
||||||||
|
||||||||
| 戦後の教科書に見る野國總管 | ||||||||
| 野國總管が小学校の教科書にのり、その功績がたたえられたのは、明治時代だけではありません。 悪夢のような戦争が終わって間もない沖縄で、戦後初のガリ版刷の教科書の中に、ふたたび野國總管が登場します。7年生(当時は小学校8年、中学校4年)の教科書に沖縄の産業の恩人として取りあげられます。 当時は、戦争による破壊から沖縄の復興がさけばれ、「新沖縄建設」を合いことばに、人びとがようやく立ちあがろうとしたときでした。そのときにも、野國總管の功績があらためて注目され、教科書に掲載されたのです。 戦後沖縄の復興のときに、「進取の気象」(ものごとに取り組む強い意気ごみ)をもって、甘藷を伝えた野國總管の生き方が、困難に立ちむかおうとする人びとに、勇気と希望を与えたのでしょう。 このように、野國總管の功績は、沖縄の社会が大きくゆれ動くときや、時代が変わろうとする節目節目に、教科書をはじめ記念碑などによってさまざまに顕彰されています。これから見ても、野國總管が私たちにのこしてくれた恩恵が、いかに大きなものであったかがわかります。 |
||||||||
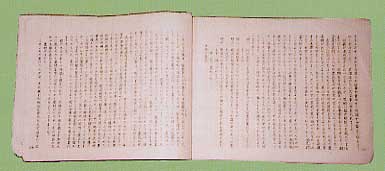 ガリ版刷教科書の見開きページ |
||||||||
| 真境名安興と野國總管 | ||||||||
| これまでお話してきたいろいろな歴れきし史の本などに書かれた内容をふまえて、野國總管の功績を明らかにし、今日の野國總管像を形づくるために、大きな影響を与えた二つの文章があります。それは、郷土史家の真境名安興によって書かれた文章です。真境名安興は、「沖縄学の父」とも称される伊波普猷らとともに、生涯を沖縄研究にささげた歴史学者でした。このような名高い郷土史研究者であった真境名安興の筆によって、野國總管の功績が記述されたことは、とても大きな影響を与えるものでした。それは本土の著作も含めて、その後の野國總管に関する記述のほとんどが、真境名安興の書いた文章にもとづいていることからもわかります。 真境名安興が、野國總管の功績について最初に書いた文章は、沖縄教育会が発行した『沖縄教育』という雑誌に掲載されたものです。沖縄教育会創立25 年を記念した「偉人伝」の特集号(1911〈明治44〉年8月)の中で、「沖縄産業界の2大恩人」である野國總管と儀間真常を取りあげて論じています。その内容は、野國總管と甘藷の伝来について、これまで見てきた家譜や歴史の本などを使いながら書かれています。真境名安興の書いたその文章は、すぐに「琉球偉人伝」という表題で、『沖縄毎日新聞』に転載されて、多くの人びとの間で広く読まれるようになりました。 |
||||||||
|
||||||||
| 琉球の五偉人 | ||||||||
| 二つ目の文章は、1916(大正5)年に発刊された、伊波普猷といっしょに書いた『琉球の五偉人』という本の中に収録されたものです。 その文章は、最初の「偉人伝」の文章とほとんど同じですが、けずった部分や新たに書きくわえた記述もあり、特に、甘藷の伝来に関する記述が大はばに書きくわえている点が注目されます。 その書きくわえたところは、一つ目は、沖縄の甘藷の伝来について、野國總管が伝える9年前にすでに宮古島に伝えられていたとする説です。二つ目は、蕃薯(甘藷)が本土に伝わる年代とその伝わった場所に関するそれまでとは違う説をのべている点です。三つ目は、甘藷畑の手入れのし方や栽培法などの改良を行った周氏金城和最についての記述です。 現在の研究では、沖縄への甘藷の伝来では野國總管が伝える前に宮古島に伝わっていたとする説には批判もあり、はっきりしていません。ただ、これまで見てきた家譜や歴史の本などから確かめることのできる点から考えると、沖縄に甘藷が伝わったのは、野國總管によって持ち込まれ、栽培されたのがもっとも早かったという説の方が説得力があり、ほぼ間違いないと思います。 真境名安興の書いた二つの文章は、野國總管の功績をほめたたえるために、その後、さまざまな形でくり返し活用されていくことになります。それ以降、野國總管の功績は、真境名安興の書いた文章をもとにして、沖縄教育会の出版する本や沖縄史蹟保存会(1922 年)の建立する顕彰碑などによって、たたえられて、さらに広まっていくようになります。 |
||||||||
|
||||||||
| 沖縄教育会と野國總管 | ||||||||
| 沖縄教育会は、1922(大正11)年に郷土の偉人をたたえ、その功績をコンパクトにまとめた『七偉人小伝』という本を発行し、1924
年には沖縄をおとずれる人びとのための「歴史文化の栞」として編集した入門書である『琉球』が刊行されます。 二つの本の中で、真境名安興が書いた文章をもとにして、野國總管の功績がわかりやすくまとめられています。とりわけ『琉球』は、沖縄文化のありのままの姿を他府県の人びとに理解してもらうための入門書として、歴史家によるむずかしい文章ではなく、教育者によってわかりやすく記述されています。野國總管に関することがらも、やさしい文章で表現されて一般向けに紹介されています。 もう一つ、注目すべきことがあります。これまでは、野國總管の功績は教科書やいろいろな本によってたたえられてきましたが、書物だけでなく顕彰碑や墓碑によってほめたたえられるようになってきたことです。顕彰碑というのは、功績をほめたたえた文章を石にきざんで、記念として残すことです。墓碑というのはお墓に建てる石のことですが、それにも亡くなった人が、生きている間に成しとげた功績などをきざむことがあります。 1922 年、真境名安興など、郷土の歴史を研究している人びとや、学校の先生などを中心にして、沖縄の史蹟(歴史上大きなできごとのあったゆかりの地)のたいせつさとその保存を人びとに知らせるために、「沖縄史蹟保存会」が設立され、発足します。 沖縄史蹟保存会は、沖縄教育会とともに、沖縄の歴史文化の研究をするだけでなく、貴重な史蹟を紹介するため、代表的な史蹟にその由来などを記した標柱を建てて顕彰する活動などを行いました。 |
||||||||
|
||||||||
| ガリ版刷教科書 | ||||||||
| 戦争が終わって、1945年8月には米軍政府は沖縄教科書編集所を設置します。 その編集の方針は、軍国主義や日本の教材を使わず、人類愛に基づく新たな理想を追求するという米軍の指示により、沖縄を対象にした教材を中心に編集されることになります。「国語」という名称も、戦前の日本の教科書との違いを表す意味で、「読方」に変えられます。戦後沖縄の最初のガリ版刷り教科書で、野國總管が取り上げられ、各学校に配られますが、1948 年に紙と設備不足により停止になり、その後本土からの新しい教科書が使用されます。 |
||||||||
| 琉球の五偉人 | ||||||||
| この本は、1916(大正5)年に、偉人伝として琉球を代表した政治家である羽地朝秀、蔡温、宜湾朝保と、教育会と産業界を代表する程順則と儀間真常を取り上げてまとめたものです。政治家は伊波普猷が、産業と教育家は真境名安興の筆によります。この本では、偉人のひとりとして野國總管は取り上げられてなく、儀間真常との関係で述べられているだけです。しかし、その文章は、今でも野國總管の功績を考えるうえで、基本的な論文として大きな影響を与えています。 |
||||||||
| 沖縄教育会と七偉人小伝 | ||||||||
| 大正時代の後半になると、沖縄でも、郷土の歴史や文化の見直しがおこるようになります。そして学校の先生方を中心に、沖縄の歴史や文化の学習が盛んになり、その知識を生かして、人物や史蹟を顕彰した記念碑や名所案内のための標柱を建てる活動がおこります。1922
年に設立された沖縄史蹟保存会は、郷土史家や学校の先生たちが中心になり琉球の七偉人の記念碑を建立しますが、その一人に野國總管が選ばれて、お墓の横に建てられました。 |
||||||||
| 首里城を救った話 | ||||||||
| 大正時代の後半に、学校の先生方を中心に郷土の歴史や文化に関心が高まり、沖縄史蹟保存会が設立されたのですが、沖縄全体では歴史文化財に対してあまり関心がありませんでした。それを示す有名なできごとが、1924 年の首里城取りこわし工事の中止です。当時、首里市が古くなった首里城を取りこわそうとしたとき、それを救ったのは沖縄の人ではなく、沖縄文化を高く評価していた鎌倉芳太郎と伊東忠太の本土の研究者でした。政府に首里城の保存を訴えて、取りこわし工事が始まる直前に中止させて、保存させたのです。 |