| 1 野國總管の強い意志 | ||
| 總管職と久米村 | ||
| 野國總管は中国から、甘藷の苗を、どういういきさつで沖縄に持ち帰ったのでしょうか。 そのことを考える前に、野國總管の人がらやその当時の野国村のようすについて、お話をすることにします。 |
||
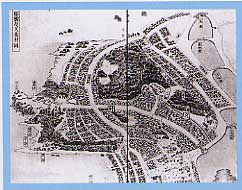 明治のはじめのころの久米村の地図(伊知地馨『沖縄志』より) |
||
| 總管が北谷間切の野国村で生まれ、進貢船の總管職に任命され、乗組員として中国に渡ったことは、前にもお話したとおりです。一口に總管職に任命されたとはいっても、それは私たちが考える以上に、特別なことだったのです。そしてそのことは、野國總管の人がらや功績を考えるうえで、大へん重要な意味をもっています。 それまでの進貢船の總管職といえば、中国へ渡る航路のようすを知りつくし、行き来した経験があり、中国について知識のある久米村の若者がえらばれるのがふつうでした。当時は、總管職に、航海になれている地方の優秀な若者が選ばれることもまれにありましたが、士族でもない野國總管が選ばれたことは、とても異例なことだったといえます。当時の野国村には野国川という川が流れ、比謝川と同じく山原船が行き来しており、たぶんそこで航海の技術を学んだのだと思います。それが野國總管にとって大きな力となったのだと想像されます。そのことは、野國總管が非常に優秀な若者だったことを意味するだけでなく、進貢船の總管職につくために、野国村の環境の中で、大へんな努力を積つみ重かさねていたことを示しています。 |
||
| 總管のこころざし | ||
| しかし、野國總管が優秀な若者で、進貢船の總管職につくために大へんな努力をしたということだけでは、中国から甘藷の苗なえを、野國總管が持ち帰ってきたことの説明として、十分ではないように思います。 なぜ、野國總管は中国から甘藷の苗を持ち帰ってきたのでしょうか。その点にこそ、農村である野国村出身の野國總管が、進貢船の總管職に選ばれるために努力した本当の理由があるように思います。 幼いころから總管が目にしていたのは、生まれ育った野国村やまわりの村びとの貧しい暮しぶりでした。台風や日でりがつづくと、作物は不作になり、すぐに毎日の食物に困りました。このような村びとの暮らしを、なんとかしてよくしたいという気持ちを、野國總管は人一倍つよく持つようになりました。そのために、自分に何ができるかを真剣に考える日々がつづきました。そして、その中から、どんな困難にぶつかっても、人びとを苦しみから救おうという強い意志がうまれたのです。その強い意志が、進貢船の總管職につくための努力として、野國總管の背中を押したのだと思います。さらにそのことが、野國總管に、事前に見つかると總管職の役職まで失うかも知れない、また自分の身さえも危険にさらすかも知れない、中国から甘藷を持ち出すという行動にむかわせた、本当の理由があるのだといえるのではないでしょうか。 その背景には、野國總管の中に、貧しくて弱い人びとに手をさしのべる思いやりの心と、自分で思ったことを成しとげるために意志を持ちつづける強い心があったからだといえます。そして、その野國總管の思いやりと強い心が、まわりの人びとから信頼を勝得えて、進貢船の總管職に選ばれる大きな理由になったのです。そしてさらに、野國總管の中にそのような思いやりの心と強い心をつちかったのが、生まれ育った野国村であり、そこで貧しさにあえぐ人びとの苦しみを何とか救いたいという思いであったことはすでに述べたとおりです。  進貢船の図 野國總管もこのような進貢船に乗って中国へ渡りました。(沖縄県立博物館蔵) |
||
| 農村の食料事情とききん | ||
| 甘藷が伝えられる前の沖縄の主な農作物は、稲・麦・アワ・ヒエなどの雑穀類と、ヤマイモ(ヤマイモ類)・タロイモ(サトイモ類)などのイモ類でした。ところが、農民が主食としていたのは、お米ではなく麦やアワ・ヒエなどの雑穀類とヤマイモ類でした。アワ・ヒエなどに野菜をくわえた雑炊とヤマイモを食べるというのが、毎日の食事だったのです。お米を口にできたのは、一年のうちでも祭りや行事といった特別の日だけにかぎられていました。毎日、お米を口にできたのは、那覇・首里に住む一部の位の高い士族だけでした。 稲や麦・アワなどといった穀物は、実のなるたいせつな部分が地上にさらされているため、台風が襲ったり、日でりがつづいたりすると大きな被害をうけることになります。 沖縄は台風の通り道といわれ、かんばつに見まわれることがとても多い地域です。それは、現在でもあまり変わりありません。ただ、ダムがたくさん造られ、毎日の用水に不自由を感じることがほとんどなくなりました。また、家もコンクリート建てが多くなり、台風の恐さをそれほど実感することもありません。しかし、台風は毎年のように襲ってくるし、かんばつも数年に一度の割合いで発生しています。 昔は、台風とかんばつのために、作物が収穫できずに、ききんとなって、たくさんの人が命を落とすということがたびたび起こりました。17 世紀から18 世紀にかけて、琉球では10 年に1度の割合いで、ききんが起こったという記録が残っています。沖縄の人びとは一生のうちで数回もききんにあい、飢えに苦しんだ経験を持っているということになります。その最大の原因は、夏から秋にやってくる台風とかんばつでした。台風とかんばつによるききんの悲惨な状況は、琉球の歴史の本などにも数多く記されています。  大正時代の野国川河口のようすです。 1709 年に起こった大きなききんのときは、夏から秋にかけて暴風雨が7回も襲ってきて、翌年の春には大きな被害をもたらしたと伝えられています。記録によると、そのときの餓死者は3199 名にものぼったとあります。中には、お金があっても買う食料がなく、しかたなくお金を枕にしながら、死んでいった人もいたと伝えられています。お金さえ出せば必要なものが何でも買える現代の私たちには、想像もできないことです。 ききんのむごたらしさは、口ではいい表せないほど悲惨なものであり、琉球では、そのようすをたんに〝ききん〟とはいわず〝餓死年〟とよぶことが多いと記されています。 小さな島国である琉球列島は、ひとたび台風やかんばつに見まわれると、作物に大きな被害が出るだけでなく、多くの餓死者が出たわけですが、その原因として、つぎの二つが考えられます。 一つ目が、琉球列島が小さな島国で、水資源がとぼしく、台風の通り道になっているということです。二つ目は、農作物の栽培に必要な溜池などのかんがいが行われていなかったということです。そのうえさらに、農村地域の人びとが、台風やかんばつに弱い麦やアワ・ヒエなどの穀物類を主食にしなければならなかった食料事情があったといわれています。  恩納村安富祖の水田 |
||
| 進貢貿易と久米三十六姓 | ||
| 明国は、琉球が朝貢関係を結ぶと、「琉球優遇策」(琉球を手厚くもてなす)として、琉球に大型海船を無料で与えるとともに、航海技術や外交、商活動にたけた中国人を派遣しました。海船の無料供与は160
年間も続きます。派遣された中国人が住む区域は他の東南アジア地域にもありましたが、琉球では那覇久米村に住み、一般に「久米三十六姓」とよばれています。16
世紀後半に琉球の海外交易が弱まった理由には、本文でのべたほかに、海船の無料供与の打切きりと、久米三十六姓が九姓にまで減った点も指摘されています。 |
||
| 15 世紀後半の与那国島のようす | ||
| 15 世紀後半に与那国島に漂着した朝鮮の済州島民が、見き聞した記録があります。それによると、比較的水が豊富な与那国島では二期作が行われ、アワもつくられていましたが、三食とも米食で、土器で米をたき竹筒で型ぬきした、にぎり飯が木の葉にのせられて配られていたとあります。しかし、与那国島とは違って水の乏しい沖縄の他の多くの地域では、アワ、ムギ、ヒエなどの雑穀とヤマイモが中心で、米が主食だったわけではなく、食糧事情は天候に大きく左右されていました。 |
||
| 台風について書いた本 | ||
| 1700 年代初期には、台風が移動することやその位置を知ることなど、まだできなかったといわれています。しかし、中国へ実際に渡航し、そこで学んだ知識によって、東シナ海の気象に通じていた琉球人がいました。名護親方で知られている程順則です。彼は、1708
年に『指南広義』という本を発刊し、その中で琉球と中国との渡航コースの気象や、前線や冬期の低気圧と夏の台風について書いていますが、現在から見てもさほど間違いはなく、高く評価されています。 |
||
| 沖縄のききんとソテツ | ||
| 野國總管によって沖縄に甘藷がもたらされたことで、多くの人びとが救われました。しかし、台風やかんばつが長くつづいた場合、その甘藷さえできず、餓死者が出ることも少なくありませんでした。そのとき注目されたのが、ソテツでした。ソテツは有毒ですが、実やみきの部分にはデンプンが多いので食用として活用されたのです。琉球王府は、ききんに備えて農民にソテツ栽培をすすめ、19 世紀の初めには蘇鉄方という役所をもうけて、その植え付けを指導したほどです(34 ページの図表を参考)。 |