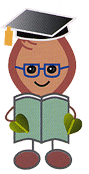| 1 国際性を学ぶ | ||
|
||
| まず一つ目の「国際性」について考えてみましょう。 国際性とは、沖縄や日本などという限られた地域や国だけでものごとを考えたり、行動したりするのではなく、違う価値観をもつ地域や国の文化や政治に対する深い理解をもって、考えて行動することをいいます。国際性を身につけるということは、このようなものの見方、考え方のできる能力を身につけることをいいます。 国際社会、国際政治、国際問題あるいは国際化など、頭に国際という文字をつけたことばが、テレビや新聞などではひんぱんに出てきます。皆さんもたびたび耳にすることばだと思います。現在では、日常語として会話の中にもごく自然に登場するようになりました。 それでは、野國總管の時代はどうだったのでしょう。野國總管が活躍した17 世紀初めごろの世界のようすを見てみましょう。 琉球王国として一つの国家を形成し、大交易時代を経験していた沖縄社会は、実に誇らしいことですが、はるか500 年も前に、すでに国際化の時代の先導者の役割を果たしていたと思います。ところが、江戸幕府を成立させ、封建国家(上下関係を重んじ、個人の人格や自由を軽んじること)への道を歩んでいた日本は、国際化とはほど遠い社会を形成しつつあったといえます。 一方、ヨーロッパの国々は、新航路の発見を機に、大航海時代をむかえており、世界へむけて門戸を開く、国際化への道をつき進んでいました。 さて、野國總管が甘藷と出会う舞台となった中国に目をむけてみましょう。 当時の中国は、世界の中でもすぐれた文化をもつ先進国の一つに数えられ、政治や経済の面でも、アジアの中心として大いに栄えた大国でした。沖縄が中国や日本と東南アジアの国々を結ぶ中継貿易の拠点として大きく発展できたのも、中国との深い結び付きがあったからだといえます。それともう一つ、忘れてならないのが、沖縄が中国ばかりでなく、日本や東南アジアの国々に対しても広く門戸を拓いた社会を形成していたことです。 このように外国に対して門戸を拓く社会の中で生きた野國總管が、学問する機会を得、先進国である中国に目をむけるようになったのは、決してめずらしいことではなかったと思います。生まれ育った野国村の貧しさに心をいため、学問によって高い志を内に秘めるようになった野國總管が、やがて中国行きのチャンスにめぐり合うことになります。總管はそのチャンスをのがしませんでした。進貢船の總管職という役職を得て、甘藷の導入という偉業を成しとげるのです。 その大きな力となったのが、外国に扉を開く社会をとおして、違う国々に対する深い理解と、積極的に交流を図ろうとする強い意欲でした。それこそわたしたち嘉手納町のめざす〝国際化教育〟といえるものです。 私たちの先人は、星のまたたく夜の海を航行するとき、その目印として〝にぬふぁ星〟(北極星)をたくみに利用しました。野國總管は〝にぬふぁ星〟となって、私たちの大きな道しるべとなっているのです。 |