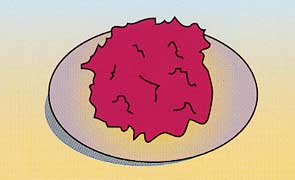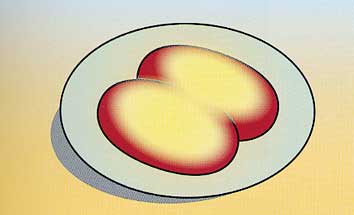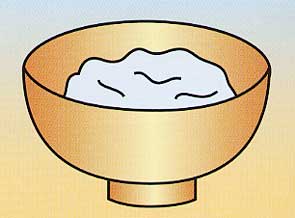| 2 琉球料理に見る甘藷のメニュー | ||
| ニーンム(煮いも) | ||
|
||
| 水炊きにした甘藷は、皮をむいて丸かじりにして食べます。もっともシンプルでポピュラーな食べ方ですが、主食として1日に何度も食べるわけですから、手のこんだ料理にすることができなかったのは、しごく当然のことだといえます。むいた皮は、家畜のエサとして利用されました。 |
||
| ンムニー | ||
|
||
| ●作り方● | ||
| 甘藷の皮をむいて、よく水洗いし、適当な大きさに切ってニーンムのように水炊きにします。炊きあがったら、炊き水をこぼし、ナベの中でしゃもじなどを使ってねりくだき、アンコ状に仕しあ上げます。 |
||
| ンムクジ・ムーチー | ||
|
||
| ●作り方● | ||
| ンムクジに砂糖をくわえ、少しずつ水をたらして、ぶつぶつができないようによくこねます。十分温めたナベに油をひき、こねあげてやわらかくしたンムクジを入れて炒めます。アメ色になったところで火を止めて、はったい粉(大麦などをひいた粉)をかけて、手のひらでひらたくなるまで押し、しばらく冷やしてできあがりです。 |
||
| ンムクジ・プットゥルー | ||
|
||
| ンムクジ・アンダギー | ||
|
||
| ●作り方● | ||
| ンムクジをとかしておき、つぶしておいた甘藷と粉にした黒砂糖(砂糖を使わない地域もあります)をくわえ、まぜ合わせます。それを油で揚げて仕上げます。 そのほかに、「ンムクジ」を使った料理として、子どもたちが大好きな「ンムクジ・ヒラヤチー」や「ンムクジ・ポーポー」などがありました。 |
||
| ンムカシ・ターチーメー | ||
| ンムカシというのは、甘藷からでんぷんを取り出すときに残るいものカスのことです。ンムカシを発酵させて手で適当な大きさににぎり、直射日光や日かげで乾燥させたものを「ンムカシ・アーシー」といい、いざというときのために貯蔵しておいたのです。食糧が底をつきそうになったときや、長雨などでいも掘りができない日がつづいたときなどは、ウムカシを使って料理をこしらえていました。 |
||
| ●作り方● | ||
| ンムカシ・アーシをうすでつきくだき粉にしたものを、ふっとうさせたお湯の中に入れて、煮ながらかきまぜてつくります。ほとんど味付けもしないで、お汁などをそそいで食べることもありました。 |
||
| カンダバージューシー | ||
|
||
| よく似にた料理として、「フーチバー(よもぎ)ジューシー」や「ンジャナーバー(ほそばわだん)ジューシー」などがあります。フーチバージューシーはからだに良いとして、今でも人気のある沖縄料理のメニューになっています。 |
||
| カンダバー汁 | ||
| 現代のように、1年中野菜が食べられる時代とは違って、かつての沖縄では夏場になると野菜がきょくたんに少なくなりました。カンダバーは、貴重な夏野菜の一つとして、なくてはならないものでした。 みそと塩で味付けしたお汁に、カンダバーを入れただけのとてもシンプルな料理ですが、独特の香と風味があり、よく食べられました。 |
||
| 戦争と甘藷 | ||
| 1945(昭和20)年4月1日、アメリカ軍は沖縄島の中部西海岸へ上陸を開始します。その直前に、嘉手納の住民のほとんどは北部の山中へ避難していました。 アメリカ軍の攻撃から身を守るためでした。しかし、避難するときに持ち出した食糧もやがて底をつき、食べるものもなくなってしまいます。昼間は山中に身をひそめている避難民も、よいやみがせまりあたりが暗くなり出すと、食料をもとめて里へ降りていきます。戦時中とはいえ、北部には甘藷がたくさんあったからです。暗やみの中を、手さぐりで甘藷を掘るのです。こうして、飢えをしのぎ命をながらえてきたのです。 |
||
| いもとハダシの時代 | ||
| たくさんの犠牲者を出し、緑豊かな沖縄の山河を焼尽つくした戦争が終わって、収容先から生まれた郷里へ帰って、村々の復興に立ちあがった時代のことを、沖縄では「いもハダシの時代」とよんでいます。 終戦直後、着の身着のままで、はきものとてない混乱した時代がしばらくつづきます。子どもは遊ぶのも学校へ行くのもハダシ(裸足)で通し、大人はハダシのまま畑仕事に出かけるのがふつうでした。そして、3度の食事はもちろんのこと、学校の弁当も「ンム弁当」が当り前だったのです。 このように、3度の食事にンムを食べ、ハダシで働いて戦後の混乱した社会を立て直すために命がけで働いた時代のことを「いもとハダシの時代」とよんだのです。 |
||
| スルルムシの発生と臨時休校 | ||
| 農薬が現在ほど普及していない時代、スルルムシが発生すると、対抗する有効な手段がなく、人手によって1匹ずつ捕獲し、殺すよりほかに打つ手はありませんでした。学校は臨時休校となり、学級ごとに組み分けされ、虫退治をすることになります。 それぞれが石油と水を少量入れたビンを持ち、捕獲した虫を1匹1匹入れていきます。肥桶をかついだ高等科の生徒は、それを回収し、肥桶がいっぱいになると近くの海へ行き、砂浜に埋めるのです。 昭和10 年代ころの話です。 |