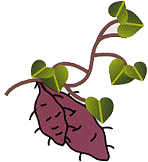| 2 工業製品と甘藷 | ||
| みそとしょうゆ | ||
| 沖縄に甘藷が導入されていらい、甘藷はみそやしょぅゆなどといった調味料の原料としても、さかんに利用されるようになります。 昭和の初めごろまで、沖縄の農家では、ンムカシ・アーシをうすでひきくだいて、えんどう豆とともに蒸し、米こうじと塩をいっしょに混ぜて、こねて仕込む甘藷のみそづくりが行われていました。 ンムカシ・アーシというのは、いもすり器(ンムシリーシリー)で甘藷をすりつぶしてでんぷんをつくるとき、でんぷんをすっかり取り去らずに、いものかすといっしょに手の中で軽くにぎり、それを直射日光や日かげで乾燥させ、たくわえておいたものです。戦前までどこの家庭でも、いざというときの食料としてつくりおきしていました。 1700 年代ごろの沖縄では、農家がお米を使ってこうじをたてて、みそやしょうゆをつくることは許されていませんでした。お米はすべて上納(税として王府におさめること)しなければならなかったのです。農家のつくるみそやしょうゆの原料はウムカシ・アーシや甘藷のチップ、それに大豆や小豆、アワ、黍などといった穀物でした。 その時代のみそやしょうゆの作り方を記録した資料がなく、正確な製造方法はわかりませんが、ほとんど同じ方法で製造されたとされる、ソテツの粉を使ったみその作り方が伝えられています(蔡温の著した『農務帳』の別冊)。 その中に「湯を煮えたたせた中に、ソテツの粉をそろそろ入れる。そのとき、かたまりが入らないように注意する。そして、煮えないぶつぶつの粉のかたまりができない程度に焼き固める。それを冷やし、こうじと塩をくわえて、うすでひいて混ぜ合わせて仕上げる」と、みその作りかたが記録されています。 同じ方法で、ンムカシ・アーシ、大豆、小麦、塩はもちろんのこと、ほかの豆類を使って、甘藷のみそや甘藷のしょうゆもつくられていた、と考えられています。 |
||
| ンムクジ(甘藷のでんぷん) | ||
| ンムクジというのは、甘藷を原料としてつくったでんぷんのことです。その作り方はいたって簡単で、戦前の沖縄ではどこの農家でも自家製のンムクジをつくっていました。 甘藷をすりおろして、よくこし、いもくずなどの余分なものを取り除いて、抽出してつくります。ンムクジはよく乾燥させて、たるや壷などに入れて保存し、必要なときに取り出して料理していました。“ ンムクジ・ムーチー” や“ ンムクジ・プットゥルー”“ ンムクジ・アンダギー” などはよく知られた琉球料理です。 |
||
|
||
| ところが、外国から安いトウモロコシが入ってくるようになって以来、甘藷のでんぷんはだんだん姿を消していきました。でんぷんの原料としては、甘藷よりトウモロコシがはるかに安いからです。 |
||
| ンムザキ(いもの焼酎) | ||
|
||
| お米を原料としてつくられる泡盛は、琉球王府への献上用のもので、一般の庶民がとても口にできるものではありませんでした。そこで、庶民が飲める酒として考案されたのが、甘藷を原料としてつくられた「ンムザキ」とよばれる「甘藷の焼酎」です。ンムザキの製造技術は、泡盛をまねたものであったとしても、沖縄の人びとが自らの手によってあみ出したものであることには違いがありません。 アジア太平洋戦争ですべてを失った沖縄の人びとに、復興への勇気と活力を与えたのは、この「ンムザキ」であったといわれていますが、残念ながら現在では製造されなくなってしまいました。 |
||
| いも焼酎 | ||
| ひとりの技術者の力ではなく、庶民の知恵として生まれた沖縄の「ンムザキ」は、戦後の混乱期をぬけ出す中で姿を消けしてしまいました。しかし、同じように、甘藷を原料としてつくられる鹿児島県のいも焼酎の製造は、産業として大きく発展し、現在では、たんなる特産品としてのワクをとびこえて、日本を代表する銘酒の一つにかぞえられています。 | ||
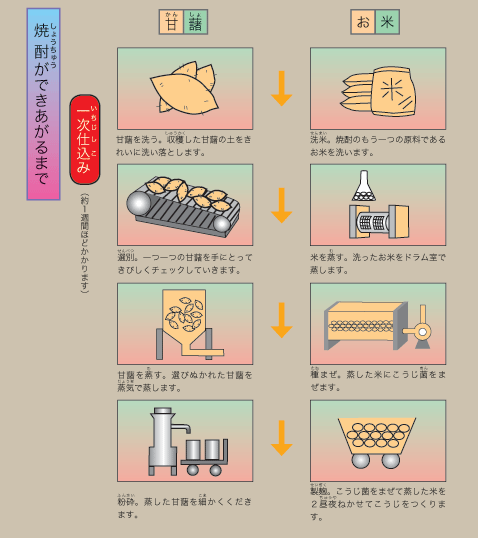 |
||
| 鹿児島県の「いも焼酎」は、甘藷が全土に広まる1700 年代には本格的につくられるようになり、以来、300
年近い歴史をきざむことになります。 「焼酎はいもに始まっていもに終わる」といわれるほどに、原料である甘藷には強いこだわりをもち、その取りあつかいには細心の注意がはらわれているとされています。たくさんある焼酎づくりの工程は、ほとんど機械化された現在でも、甘藷の選別だけは、昔ながらの人の手によって行われています。甘藷の両はしを切り落とし、傷や虫くいの部分をていねいに取りのぞき、おいしい部分だけが原料として使われているのです。 一次仕込み、二次仕込み、蒸留と大きく3つに分けられる「いも焼酎」の製造工程を絵を使って再現してみます。 |
||
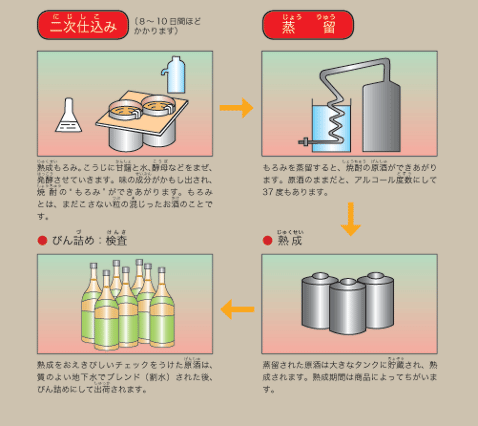 |
||
| ガソリンの代用品のアルコール | ||
| アジア太平洋戦争の末期になると、海外から石油の輸入ができなくなり、日 本軍は飛行機を飛ばすガソリンがなくなります。そこで考え出されたのが航空 燃料として、甘藷を原料としてアルコールをつくることでした。 うす切りにしたなまの甘藷を、ふかしてこうじカビと混ぜ、寝かせてモロミ をつくり、それを蒸留したのをガソリン代用のアルコールとして利用しようと したのです。そのとき使われた甘藷が、沖縄生まれの「沖縄100 号」とよばれ ていた品種でした。ガソリン代用のアルコールをつくるために、日本全国で栽 培されました。 |
||
| あわもりの名称の由来 | ||
| 蒸留酒をつくる技術は、13 世紀ごろに中国に伝えられ、そこからシャム(タイ)などの東南アジアの地域に広まっていきました。沖縄へは15
世紀ごろに、シャムからもたらされたと伝えられています。 「あわもり」という名まえの由来についても、いろいろな説があります。昔、泡盛の原料に「粟」を用いたから、あるいは薩摩藩(鹿児島県)が九州の焼酎と区別するためにつけたものだとする説などです。一般には、泡を盛ってアルコールの度数や質をはかったことから、「泡盛」という名まえがついたと考えられています。 |