| 3 甘藷よもやま話 | |
| 沖縄各地の、甘藷にまつわる語り伝えられた物語や神話、伝説を調べてみたのですが、どうしたわけか、なかなか見つかりませんでした。ここでは、甘藷の登場する〝よもやま〟の話を、いくつか紹介することにします。 |
|
| もーいー親方の話 | |
| もーいー親方といえば、琉球王国時代の人で、頓知の利いた人としてよく知られています。特に子どものころの話は有名で、本にもとりあげられているので、皆さんの中には知っている人もいると思います。 もーいー親方は、子どものころは、ぜんぜん勉強しない子でした。あまりにも勉強しないので、父や母も大へん心配したそうです。ところが本人は、親の心配をよそに、昼間は遊んでばかりいました。しかし、夜になると、ホタルをたくさんつかまえてきては、煮たいもにつけて、それを灯にして床下に隠れて勉強をつづけたそうです。こうした努力のおかげで、とても偉くなった人です。 ホタルの灯で勉強するという話は、今の小学生や中学生の皆さんには、わかりにくいかも知れません。 |
|
| 昔は、ホタルがたくさんいました。実にたくさんとれたのです。ホタルの灯は蛍光灯の明かりによく似ています。不思議なことですが、ホタルは死んでも灯は消えないのです。それに、モーイー親方が生きていた時代は、毛筆で字を書くので、大きな字になります。ですから、ホタルの灯でも十分読めたというわけです。 この話は「よく遊び、よく学べ」ということを教えたかったのかも知れませんね。あるいは「人は見かけによらない」ということをいいたかったのかも知れません。 |
 |
| いもを盗んだ話 | |
| 与那城町の宮城島に、子だくさんのとても貧しい家がありました。食べるものもありません。夜になると、お金持ちの家の畑に行って、いもをこっそり掘っては子どもたちに食べさせていました。夜中に、畑が荒らされて、いもが掘り盗られていることに気づいた畑の主が、いもどろぼうをつかまえることにしました。畑に身を隠して、いもどろぼうのやってくるのを待ちかまえていました。 |
 |
|
その夜もやってきたいもどろぼうは、「子どもたちが一人前になったら、必ず恩返しさせますから、許してください。」と、一言あやまってから、いもを掘り始めました。その一言を聞いた畑の主は、飛び出して、「これからは毎日、いもを掘ってよろしい。」と許してやりました。 子だくさんの貧しい人はやがて金持ちとなり、いもどろぼうを見のがしてくれたうえに、いもを掘ることも許してくれたお金持ちに恩返しをし、親戚になることができたそうです。 |
|
| カライモを拝む話 | |
| 種子島の西之表市に伝わる話です。江戸時代のことです。 種子島の人が大隅半島の根占というところに用事があって出かけたときのことです。泊まった宿の夫婦が、カライモを炊いて床の間に供えて、朝夕拝んでいることを知りました。種子島の人は、不思議に思い、そのわけをききました。 宿の主人は「薩摩からカライモを伝えた種子島の楢林公さまへ、感謝のお供えです。カライモのおかげで、私たち下々の者もこうして飢えることなく暮らしていけるのです。大隅はもちろん、薩摩全体、このご恩をこうむらない者はひとりもありません。」と、いうのです。 種子島の人は、これを聞いて大へん感謝し、またこのことを、はじめて知ったことを恥ずかしく思った、ということです。 |
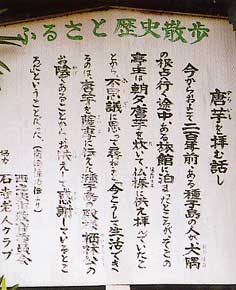 唐いも芋を拝む話が記された立看板 |
| 巨大ないも | |
| 江戸時代、越後の国(現在の新潟県)は猿沢に百姓五助という者がいたそうです。この五助の畑にできたいもが、とても大きなもので、長さが3尺じゃく(約90cm)あまり、重さが100
貫(約60 kg)もありました。世にも珍しいことだということで、役人立ち合いのもとで掘り出し、領主に献上することになりました。領主は大喜びし、五助におほめのことばをかけ、黄金も与え、いもを持ち帰らせたということです。 |
|
| ミーンム(芽いも)掘りの親子 | |
| ミーンムというのは、いもを掘った後、取り忘れて畑の中に残り、それがやがて芽を出した甘藷 のことをいいます。大きいいもは見落とすことはありませんが、小さいいもは取り忘れてしまうこともあるのです。 ここに紹介する「ミーンム掘り」の話は、新屋敷幸繁という大学の先生が、聞いたという話からまとめたものです。 沖縄戦の前のことです。耕されたよその人の畑を見てまわり、畑の主が見落としたミーンムを探しては、それを取って食べて暮らしている親子がいました。子どもはまだ小さく、母親がおんぶしていました。そんな親子を見ても、村人はだれもとがめようとはしませんでした。しかし、母親はそんな暮らしを恥ずかしいと思い、村人に顔を見られないようにしていました。人が母親の顔を見ようとのぞき込むと、おんぶされた子どもは、母親の顔が見えないように隠すのでした。そんなこともあって、村人は母親の顔をのぞこうとはしなくなりました。 ある日、いつものように我子をおんぶした母親は、ミーンムの隣に大きないもを見つけました。思わず、そっと取ってしまいました。家に帰って、今日取ってきたミーンムをひろげました。大きないもが一つ混じっていました。それを見た子どもが急に泣出してしまい、いっこうに泣き止もうとはしません。子どもは何もいわず、ただ泣くだけなのです。 とほうにくれた母親は、しばらくしてやっと子どもが泣いている意味がわかりました。 |
|
| 夕暮れの中、子どもを背負ってミーンムを取った畑にもどりました。そして、一つだけ混じっていた大きないもを畑にもどしました。ずっと泣きつづけていた子どもが、それを見て泣き止みました。親子は畑を離れて、家路につきました。 沖縄戦が起こり、そして終わりました。戦後の食糧難の中、ミーンム掘りをする人が増えました。ミーンム掘りをする人が増えたのを知った親子は、二度とふたたび畑に姿をあらわすことはありませんでした。村人たちは、親子のその後のことを心配しましたが、その消息は今もって誰だれも知らないということです。 |
 |
| いも弁当 | |
| 皆さんは、学校に弁当を持っていくことはありませんね。給食センターでつくったのを、いっしょに食べています。しかし、1950
年代ころまで、沖縄には学校給食というのはありませんでした。それで、それぞれが弁当をもって登校してきたのです。毎日の主食がおいもですから、当然、弁当もいもでした。丸煮にしたいもを風呂敷につつんだりして持っていったのです。 弁当箱が普及するようになると、ンムニーを入れたり、輪切りにしたいもを油で炒めたものや、おかずを入れたりして、工夫もこらされるようになったのです。 |
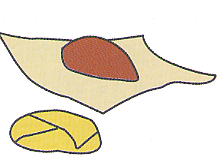 |
| 甘藷と旗頭 | |
| 旗頭というのは、お祭りのときに出される幟の一つです。那覇や与那原の綱引きでおなじみのものです。八重山の旗頭は、一級の作品がそろっています。 嘉手納でも野國總管甘藷伝来350 周年記念のとき、「豊年」の旗頭が出ています。 黒島の仲本村の正月綱引きには、大へん珍しい旗頭が登場します。旗頭を飾るのに、本物の野菜類が使われます。野菜類の中にもちろんのこと、甘藷も登場します。今年の作物が、甘藷をふくめて豊作でありますようにという願いを込めたものなのです。 |
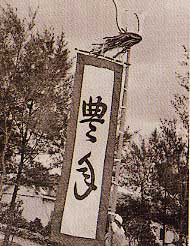 三五〇周年記念に登場した「豊年」の旗頭 |
| 正月料理 | |
| お正月は年の始まりの日として、昔から大切なお祝いの日でした。今年も家族みんなが健康で幸せでありますようにとお祈りする日です。そのときに供えるお料理で、沖縄県は豚がメインとなりますので、その料理名からウヮーソーグヮッチ(豚正月)、本土は餅がお供えの中心になるので餅正月とよんでいます。本土でも餅ではない地域もありますので、そこは餅なし正月とよんでいます。 沖縄では肉料理は言わなくとも豚肉が中心です。ですから肉といえば豚肉をさすのがふつうです。お正月に食べるために飼う豚をソーグヮッチウヮー(正月豚)といっていました。もちろん、豚のエサは甘藷が中心でした。 |
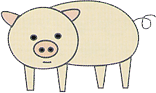 |
| イリムサーンム | |
| アリモドキゾウ虫やイモサルハムシの幼虫やサナギが塊根(いも)の中に入ったものをイリムサーンム、あるいはヒームサーンムといいます。この害虫にやられると臭みが出るだけでなく、苦みも出て食べずらくなります。それで丸煮にすることを止め、虫の入った場所を削り捨て、残りででんぷんを取りました。 ふつうのいもからでんぷんを取る以上に何度も水をかえて臭みを取りました。 捨てることなく大切に甘藷をあつかったことがわかります。 これらの害虫は昔からあったのではなく南から北上し、今は琉球列島全体に広がっています。九州以北に侵入を防ぐため、自由に本土に持っていくことが禁じられています。 |
|