| 2 にぎやかな「ンムまち」風景 | |
| 商品となる甘藷 | |
| くり返しお話してきたように、甘藷は貴重なものでした。 人間にとっても、家畜にとっても。戦前は、沖縄の地方はほとんどが農業を生業とする農家でしめられていました。それでも数は少ないものの、農業とほかの職業を兼ねる〝兼業農家〟もありましたし、漁業を生業とする家もありました。 現在では、皆さんのほとんどの家庭で、お米はスーパーや商店で買い求めていると思います。店頭にはお米が陳列されています。それと同じように、甘藷も売られていたのです。ただし、甘藷の販売は、お米のように店頭に並べて売るというより、農家の人たちが直接、買ってくれそうな家を訪ねて売ったり、市場に持っていって買い手が来るのを待って売るという方法をとっていました。沖縄各地に甘藷を売る人たちがより集まって〝市〟が開かれていたのです。そのような市は那覇にも宜野湾にもありました。売り手はほとんどが女性でした。 皆さんは知っていると思いますが、私たちの嘉手納町は、戦前は沖縄でも指折りのにぎやかな〝まち〟の一つとして知られていました。当然、「ンムまち」(いもまち)もありました。 『嘉手納町史 資料編2』に、戦前の嘉手納の「ンムまち」のようすが紹介されています。 |
|
| 嘉手納のンムまちぐゎー | |
| 戦前の嘉手納集落の南西、嘉手納大通りの中心街近くに嘉手納の「ンムまちぐゎー」がありました。朝の9時ごろから午後2時ごろまで、いも売りのおばさん達が、ンムバーキ(いもを入れたカゴ)いっぱいのいもを前にして座っていました。ンムまちぐゎーには遠くは国直や野里、読谷山あたりからもやってきて、にぎわっていたといいます。ンムバーキのほかにザルにのせた野菜束も売られていました。 買い手と商談がまとまると、その家まで運んでいくのです。おばさん達のほかに、テンビン棒にかついでアチネー(商)をする男の人もいました。いもの値段は、大正のころ(1912 ~ 1926 年)で、1斤(600g)あたりで7~9厘(1厘は1銭の10 分の1、1銭は1円の10 分の1)ぐらいで売られていたようです。相場(いもの値段)が1銭になると、女の人たちは、よい商いをしたと喜んだそうです。売った後は、お店から生活用品や耕作用品を買って帰りました。『嘉手納町史』には、このいも市のほかに「豚の市」や「牛市」なども嘉手納にあったことが紹介されています。人びとの暮らしぶりを知る上でとても貴重な記録となっています。 |
|
| 首里の汀良まち | |
| 現在の首里儀保(儀保交差点近く)に、「おもろ」で「ぎぼくびり」として謡われ、「浦添城の前の碑」では尚寧王の命令で石だたみ道が築かれたと記されている、「儀保くびり」とよばれる坂道がある。地元の人びとが今でも「儀保坂」(ジーブビラ)とよんでいる細道です。ジーブビラをのぼりつめたところは、王子や按司たちが国王をお迎え(御坂迎=ウサカンケー)した「御待所」(ウマチドゥクル)があったところとして知られています。 ウマチドゥクルより下る坂のとちゅうには、西原のいも売りの女性たちや、糸満の魚売りの女性たちでにぎわいを見せていた「汀良まち」がありました。 嘉手納に「ウムまち」ができる前までは、嘉手納の人たちもいもを入れたザルをぶらさげたテンビン棒をかついで、いも売りに行ったと伝えられています。お年寄りの話では、1日で13 銭分売ると「よい商いをした」ということで、カントーフ(豆腐にうすく塩をつけて炭火で焼いたもの)を5厘分買って、いもといっしょにそれを食べて帰ったということです。 |
|
| 甘藷と民具 その7 ヒラバーキ 甘藷の受皿ざら | |
| いもはふつう、丸煮にしたものをそのまま食たくに出して、それぞれが皮をむいて食べていました。食たくに出すのにバーキのままでは、底が深くて取りにくいものです。 それに容器が大きすぎます。そこで、バーキの縁をぐんと低くした「ヒラバーキ」が使われました。竹でつくります。 ヒラバーキにのったいもを囲んで座り、出されたお汁といっしょに食事をする。長い間つづいた沖縄の庶民の食事風景だったのです。 |
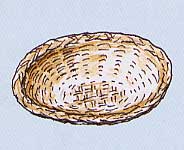 |